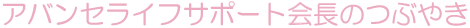新たな業態を我々の手で創りだそう
11月、日本中国友好協会の行事で中国・江蘇省南京市を訪問しました。来年度の交流計画の打ち合わせが目的でしたが、高市早苗総理の発言も影響し、歓迎会や観光は例年通り行われたものの、具体的な交流事業には互いに触れず、非常にあっさりとした訪中となりました。宗教と政治問題に触れることはタブーとされるこの国ですが、二次会では本音が語られる場面もありました。
習近平政権は「強い中国」を掲げ、ナショナリズムや愛国心を奮い立たせることで政権の正当性を強調しています。しかし、政権発足から約12年が経ち、経済成長の恩恵を受けた「勝ち組」と、教育や人脈に恵まれず定職にも就けない「負け組」との格差が顕著になり、不公平で歪な社会が広がっているように見えます。台湾併合をめぐるナショナリズムは、こうした「負け組」の不満や怒りを愛国運動に目を向けさせる狙いがあるのでしょう。その最中に日本の首相が冷や水を浴びせたため、習近平国家主席が強い不快感を示すであろうことも理解できます。
今回の訪問後改めて感じたのは、日本人は無理をして中国へ行かなくなった一方、中国人は政府が渡航規制をするまで留学生や観光客として変わらず日本に押し寄せていたことです。また、訪日する中国の知識人や富裕層は日本に好印象を持っていますが、社会的敗者層は日本への憎悪や敵対心を強く抱いていました。この両輪のコントロールは格差が大きくなる程、中国政府にとって難しく厄介になっているようです。ある中国人経営者は二次会後に私に声をかけ、「仲間を集めれば10億元(約200億円)のファンドを組成できる。利回りは5%程度でよい。その代わり介護施設を自分が所有し、林さんに運営してほしい。そして従業員を1~2名私の会社の社員にしてくれれば、私は日本の経営者ビザを取得できる。私たち中国人は自由に日本へ渡航できるビザが欲しい」と語りました。富裕層であっても自分の国の政府を信用していない悲しい現実を垣間見た瞬間でした。
さらに、9月3日に北京で開催された「抗日戦争勝利80周年」軍事パレードでは、プーチン大統領と習近平国家主席のやりとりが漏れ伝わったとも聞きます。プーチン氏は「バイオテクノロジーの発展により臓器移植で若返り、不死さえ実現できる」と述べ、習主席は「今世紀中に150歳まで生きられるという予測もある」と応じた、という話です。真偽はさておき、両者には「辞める」という選択肢は乏しく、二国の社会体制、専制主義の居心地の良さを物語っているように感じました。
さて、話題を当社の経営課題に移します。私たちは賃金の2割アップを必達目標としています。しかし現行の介護保険制度では達成は容易ではありません。この制度は「生かさず殺さず」、まるで江戸時代の農本制度のような仕組みにも重なります。この体制を私達が変えることはできませんが、このままでは職員の幸せな未来は描きにくいです。そこで体制変革の事例をいくつか考えましたが、まず一例をご紹介します。
私たちには福祉用具部門があり、現在4名の専門職員がいます。53事業所のスタッフも福祉のプロフェッショナルです。福祉用具には自助具や介助機器に限らず、実にたくさん、よくもこんなことが考えられるなと思う位様々なものが無限に存在します。先日訪問した名古屋工業大学の教授は、モーターを使わずに下肢の運動機能を10%向上させる補助具を開発されていました。介護には適さないため導入は見送りましたが、老人会やシニアNPO、シルバーセンターなどで紹介し、もう一工夫すれば十二分に市場性はあると感じました。施設を「福祉のワンストップステーション」として活用できれば、文房具通販のアスクルのように介護施設がコミッション収入を得ることも可能です。面会に訪れる家族や友人が手土産を持参せずに施設でお渡しできる気のきいたものが用意できる仕組みがあれば、施設の利便性も高まるでしょう。
業種の垣根を越えた競争も始まっています。例えば、デイサービスを利用する人の中には車が必要な人もいます。補助は必要ですが、そんな時、私たちが車の代理店を担う可能性もでてきます。20年前にドラッグストアで大根や肉が販売されることを誰が想像できたでしょうか。介護施設もまた、脱皮が必要なのかもしれません。アスクル化する介護施設―その可能性を探る時期に来ています。新たな業態を我々の手で創りだしませんか。
最後に、今年も皆さんの力に支えられました。心から感謝します。どうぞ穏やかな新年をお迎えください。
2025年12月26日(金)